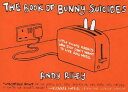"Oh,no. This is your last lesson.!" そうなんですよ。1年間(75回)の英会話スクール通いも今日でおしまい。
〆るにあたって、レベルチェックぽく自分の弱点と今後のアドバイスを教えてもらう。たとえばドラマを見ていて「これは!」と思ったフレーズは聞いて終わり、じゃなくその場で口に出してみる。そうすると「意味はわかるけど、いざ話すとなると自分で使えない」域から脱することができる、とか。
「英語学習は英文法をベースに、読む・聞く・書く・話すの4つをバランスよく進めるべし」と一般に言われる。初めてスクールに行ってみてその理由がなんとなくわかった。スピーキングの練習をすることで、学習に他の3技能とは異なる新たな視点が加わる。要するに実際に「話す相手」を得る(イメージする)ことで、「どうすればその場に適切で効果的、また感じ悪くなくコミュニケートできるか」という学習の軸ができる。
そのためには「文化や慣習の違い」に対する意識も大事ですね、と気づく。私はこの辺のことをそれまであんまり考えていませんでした。英語圏におけるそれらを意識すると、同時に自分が背負ってるであろう「日本人らしさ」みたいなものを考えるようになってくるのが面白い。で、考えるとよくわからなくなってくるんだけども(汗)、日本や日本語についての関心もちょっと増えてきました。
先日の舞踏WSで教わった「2人称」の関係と同様で、おそらく「話す」ときにいちばん強く、コミュニケーションの対象としての「相手」を意識するので、対岸(というかこっち側だけど)の自分もくっきりとし、アイデンティティを問われてくるのでしょう。また「レスポンス・タイム(相手の発言や質問に応じるまでの時間)」が関わってくるのも思うに他にない特徴で、(場合にもよるけど概して)3分かけてゴージャスな答を返すより、話しながら考えるのでいいからその場の流れを切らないほうが自然な会話としてはいい。
「英語を覚えて何を得た?」と先生に質問された。他にスキルとか社会性とかかわいげとか、世のなか渡っていくための道具らしいものがない私に英語はいくらか仕事の機会をもたらしたが、考えてみれば自分にとって英語は仕事のためではなく、そもそも「楽しいから」「好きだから」やっていることなのだった。(私ががっつりとOLしていた20代の頃はトーイックなんて世にはびこっていなかったです)
「英語を勉強してなかったら、自分は何をしていたと思う?」とも訊かれて、考えてみたけどわからなかった。私はもともと西洋(英語圏の)文化のほうに親しみがあり、自分のパーソナリティのかなりの部分がその積み重ねのうえにできているように思うので、「英語をやっていなかった」自分が何か違うこと(総務とか経理とか?…なにかしら会社/社会に役立つこと)をしていたかもしれない…というのを今の「英語(英語的なこと)によってかなり形成された」自分が想像しようとしてもできなかった。「想像できない」と言ったら、「そうでしょう」とその意味するところはじゅうぶん伝わったみたいだった。通っていたあいだ、モチベーションが落ちてきた時期もあり、そういうときはうしろめたくもなったけど基本的に英語が好きな人、というふうに見ていてくれたのかもしれない。
いちばん教わったこの先生は言語学に詳しく、舞台や表現についてわりかし深い話をしたりシェアできることが多かった。本当にお世話になりました。今の自分にとってはいい潮時と思うけれども、やっぱりちょっと寂しい。
Good luck with your life! と言われる。とても英語らしい表現であり発想。小さい頃からずっと、私が英語にきらきらした感じというか、可能性みたいなものを感じるのはたとえばこういうところです。See you around.
〆るにあたって、レベルチェックぽく自分の弱点と今後のアドバイスを教えてもらう。たとえばドラマを見ていて「これは!」と思ったフレーズは聞いて終わり、じゃなくその場で口に出してみる。そうすると「意味はわかるけど、いざ話すとなると自分で使えない」域から脱することができる、とか。
「英語学習は英文法をベースに、読む・聞く・書く・話すの4つをバランスよく進めるべし」と一般に言われる。初めてスクールに行ってみてその理由がなんとなくわかった。スピーキングの練習をすることで、学習に他の3技能とは異なる新たな視点が加わる。要するに実際に「話す相手」を得る(イメージする)ことで、「どうすればその場に適切で効果的、また感じ悪くなくコミュニケートできるか」という学習の軸ができる。
そのためには「文化や慣習の違い」に対する意識も大事ですね、と気づく。私はこの辺のことをそれまであんまり考えていませんでした。英語圏におけるそれらを意識すると、同時に自分が背負ってるであろう「日本人らしさ」みたいなものを考えるようになってくるのが面白い。で、考えるとよくわからなくなってくるんだけども(汗)、日本や日本語についての関心もちょっと増えてきました。
先日の舞踏WSで教わった「2人称」の関係と同様で、おそらく「話す」ときにいちばん強く、コミュニケーションの対象としての「相手」を意識するので、対岸(というかこっち側だけど)の自分もくっきりとし、アイデンティティを問われてくるのでしょう。また「レスポンス・タイム(相手の発言や質問に応じるまでの時間)」が関わってくるのも思うに他にない特徴で、(場合にもよるけど概して)3分かけてゴージャスな答を返すより、話しながら考えるのでいいからその場の流れを切らないほうが自然な会話としてはいい。
「英語を覚えて何を得た?」と先生に質問された。他にスキルとか社会性とかかわいげとか、世のなか渡っていくための道具らしいものがない私に英語はいくらか仕事の機会をもたらしたが、考えてみれば自分にとって英語は仕事のためではなく、そもそも「楽しいから」「好きだから」やっていることなのだった。(私ががっつりとOLしていた20代の頃はトーイックなんて世にはびこっていなかったです)
「英語を勉強してなかったら、自分は何をしていたと思う?」とも訊かれて、考えてみたけどわからなかった。私はもともと西洋(英語圏の)文化のほうに親しみがあり、自分のパーソナリティのかなりの部分がその積み重ねのうえにできているように思うので、「英語をやっていなかった」自分が何か違うこと(総務とか経理とか?…なにかしら会社/社会に役立つこと)をしていたかもしれない…というのを今の「英語(英語的なこと)によってかなり形成された」自分が想像しようとしてもできなかった。「想像できない」と言ったら、「そうでしょう」とその意味するところはじゅうぶん伝わったみたいだった。通っていたあいだ、モチベーションが落ちてきた時期もあり、そういうときはうしろめたくもなったけど基本的に英語が好きな人、というふうに見ていてくれたのかもしれない。
いちばん教わったこの先生は言語学に詳しく、舞台や表現についてわりかし深い話をしたりシェアできることが多かった。本当にお世話になりました。今の自分にとってはいい潮時と思うけれども、やっぱりちょっと寂しい。
Good luck with your life! と言われる。とても英語らしい表現であり発想。小さい頃からずっと、私が英語にきらきらした感じというか、可能性みたいなものを感じるのはたとえばこういうところです。See you around.
話しながら自分モニターしてみると、ボロボロだなぁと思う。時制、主語と述語、合ってない。中学生か。それでも会話が成立するのは、先生が我慢強い聞き手で、こちらが言葉を探すのを待ってくれてるから。1対1だと話す量は多いのは良いですが、(レッスン評価もあることだし)どうしても甘やかされることになってるなと思う。英語電池は依然として寿命40分…。
もともと写真を撮られるのが苦手で、証明写真は赤裸々ゆえにかなりイヤで落ち込む。いっつも「にこやかに!」「目を大きく開いて!」と言われる。目は大きくならない。
今月で英会話も終わり、「カウンセラー」とかいう人に「進捗と今後の学習について伺いたい」と言われ面談。継続の売り込みと思っていたら押す意志はないみたいで(ていうかこちらの希望すら訊かないってのは)、有料のオンライン教材を「一応」ご紹介するだけだった。「日本語で」話しながら、ここにディスコミュニケーションがある、と考えていた。私が「こういうことはできるようになったが、こういうことができてない」と学習の成果を話すも言葉は超えられない壁にぶつかって、落下するのを見ながらカウンセラーのお姉さんは終始おなじ笑顔のままだった。その笑顔を維持することがこの人の仕事なのだと私は思った。
今月で英会話も終わり、「カウンセラー」とかいう人に「進捗と今後の学習について伺いたい」と言われ面談。継続の売り込みと思っていたら押す意志はないみたいで(ていうかこちらの希望すら訊かないってのは)、有料のオンライン教材を「一応」ご紹介するだけだった。「日本語で」話しながら、ここにディスコミュニケーションがある、と考えていた。私が「こういうことはできるようになったが、こういうことができてない」と学習の成果を話すも言葉は超えられない壁にぶつかって、落下するのを見ながらカウンセラーのお姉さんは終始おなじ笑顔のままだった。その笑顔を維持することがこの人の仕事なのだと私は思った。
ワーク・ライフ・バランス
2012年3月7日 ELよく教わってた英会話の先生のレッスンを久しぶりにとる。演劇やってたのは聞いていたけど、大手スクールだし忙しくてやめたんだろうなと勝手に思っていたら、今もばりばりやってるそうな。春も舞台があるとかで写真入りのばりっとしたパンフレットを持っていた。「夜は教えてないし、早めに言えば休みもとれるし、仕事と両立できる」とか。
自身の就活は頓挫している(ので、ワーク以前の問題)。前職と去年とった資格の関係から、ある業界にしぼっていたけれど、結局いちばんのネックがシフト勤務でダンスが続けられなくなるだろうということ。
前職はストレスフルな環境だったものの仕事自体はやりがいがあり、ダンスはあきらめようといったんは思った。続けていてもさっぱーりぱっとしないし、プロになるわけじゃなし、いいかげん潮時かなぁと。
でもそう思うと、着実に積み上がっているのがわかって嬉しい瞬間が不思議とあって、先へつなげてくれたりする。積み上がって築かれるのは自分の身心のみならず、そういう場で出会う人々との関係でもあり、そうしたことが考えてみれば自分にとって最大の資源ではないの…。これをとったら私のLは激しく失われ、何のためのWなのかってことになりかねないのでは。こういう時期だからこそ1回1回のレッスンに救われているのも事実。
「仕事のためにダンスやめようと思ったのですが、やめられませんでした」とこちらの先生に言ったら、「君はやめられないでしょ」と笑われた。資格の勉強をいちばんサポートしてくれた人なので、「その方面にいかないかもしれない」という話をしなくてはと思いつつできずにいて、話せてよかった。
自身の就活は頓挫している(ので、ワーク以前の問題)。前職と去年とった資格の関係から、ある業界にしぼっていたけれど、結局いちばんのネックがシフト勤務でダンスが続けられなくなるだろうということ。
前職はストレスフルな環境だったものの仕事自体はやりがいがあり、ダンスはあきらめようといったんは思った。続けていてもさっぱーりぱっとしないし、プロになるわけじゃなし、いいかげん潮時かなぁと。
でもそう思うと、着実に積み上がっているのがわかって嬉しい瞬間が不思議とあって、先へつなげてくれたりする。積み上がって築かれるのは自分の身心のみならず、そういう場で出会う人々との関係でもあり、そうしたことが考えてみれば自分にとって最大の資源ではないの…。これをとったら私のLは激しく失われ、何のためのWなのかってことになりかねないのでは。こういう時期だからこそ1回1回のレッスンに救われているのも事実。
「仕事のためにダンスやめようと思ったのですが、やめられませんでした」とこちらの先生に言ったら、「君はやめられないでしょ」と笑われた。資格の勉強をいちばんサポートしてくれた人なので、「その方面にいかないかもしれない」という話をしなくてはと思いつつできずにいて、話せてよかった。
なんとなくお得な感じがしないでもない閏年。そんな日にこんこんと雪ぞ降りける。こんな日にとことこと英会話へ行く。
「Web時代の著作権」等について戦う。相手は被災地ボランティア団体のとりまとめなどもしている社会派なお方で、ソーシャル・サイエンス一般について詳しいとみた。
ひよわな論陣を張ってみるスイカ。英会話のレッスンというよりゼミの先生にやりこめられてる風に、激しいツッコミがくる。いっぱいいっぱいにリバッタルしてみる。著作権についてかなり適当なことを言い連ね、運がよければ大体あってる。詳細知らないところは(そりゃ知らないさ)別な話題を振って逃げる。そして自らの電池切れる…。
ふだんは先生が「合わせてくれてる」のであって、己の英語力の拙さを改めて知る。レッスン外の現実ではこのように実弾が飛んでくるのでありましょう。先生は後でにやにやしながら「よく防衛してた」と言ってたけど私の言い分のいい加減さ加減もばれていたでありましょう。でも面白かった。「ディスカッション」というテキストはこのように進めるのが本来、正しいのではないか、と思ふ。このくらい追い詰めてほしい。留学したりして授業でこのようにしごかれるならそりゃ真に上達するだろう。うらやましい。
「従来のメディア(e.g.本)」と「デジタルメディア(e.g.電子ブック)」どちらがいいか、という話。私は本がいいと言い、「デジタル化されると何かが失われる気がするから」としか説明できなかったのだが…データにすればコンテンツは保持されるが、個人的にはそれはもう「本」ではない気がする。存在の質が変わってしまう。無人島に流されたとき「リーダーズ英和大辞典」があったら日々1ページずつ読むだろうが、電子辞書があってもそこで読む気に自分はならないと思う。たとえ電池が残っていたとしても。
「Web時代の著作権」等について戦う。相手は被災地ボランティア団体のとりまとめなどもしている社会派なお方で、ソーシャル・サイエンス一般について詳しいとみた。
ひよわな論陣を張ってみるスイカ。英会話のレッスンというよりゼミの先生にやりこめられてる風に、激しいツッコミがくる。いっぱいいっぱいにリバッタルしてみる。著作権についてかなり適当なことを言い連ね、運がよければ大体あってる。詳細知らないところは(そりゃ知らないさ)別な話題を振って逃げる。そして自らの電池切れる…。
ふだんは先生が「合わせてくれてる」のであって、己の英語力の拙さを改めて知る。レッスン外の現実ではこのように実弾が飛んでくるのでありましょう。先生は後でにやにやしながら「よく防衛してた」と言ってたけど私の言い分のいい加減さ加減もばれていたでありましょう。でも面白かった。「ディスカッション」というテキストはこのように進めるのが本来、正しいのではないか、と思ふ。このくらい追い詰めてほしい。留学したりして授業でこのようにしごかれるならそりゃ真に上達するだろう。うらやましい。
「従来のメディア(e.g.本)」と「デジタルメディア(e.g.電子ブック)」どちらがいいか、という話。私は本がいいと言い、「デジタル化されると何かが失われる気がするから」としか説明できなかったのだが…データにすればコンテンツは保持されるが、個人的にはそれはもう「本」ではない気がする。存在の質が変わってしまう。無人島に流されたとき「リーダーズ英和大辞典」があったら日々1ページずつ読むだろうが、電子辞書があってもそこで読む気に自分はならないと思う。たとえ電池が残っていたとしても。
と言ってはなんだが311のときはデマが流布しましたね、という話。情報の過多(正誤両方が流れ、ときには誤りの修正がなされなかった)によっても、情報の不足(特に原発について、専門的知識の欠如から非専門的な情報に左右された)によっても、悪意によっても善意によっても起きる。
個人的に実害はなかったけど、私が当時、不安だったのは社会全体として感情のたががゆるんでいるように感じられたこと。平時には覆われているものがむき出しになっているというか。それから「日本人はあのカタストロフィーのさなかで列をつくって待っている!なんたる忍耐強さ」などと国外で報じられたけれども、それは「当日は誰も被害の大きさがわかってなかったから(いつものように)そうしていただけではないか、と思う」という話。
この若い兄ちゃんも教え方上手い。テキストの進め方を工夫しているし、「こういうところを直したい」というと練習を考えて応じてくれる。Anyways,と言うのがクセ(若者の流行り?)。
個人的に実害はなかったけど、私が当時、不安だったのは社会全体として感情のたががゆるんでいるように感じられたこと。平時には覆われているものがむき出しになっているというか。それから「日本人はあのカタストロフィーのさなかで列をつくって待っている!なんたる忍耐強さ」などと国外で報じられたけれども、それは「当日は誰も被害の大きさがわかってなかったから(いつものように)そうしていただけではないか、と思う」という話。
この若い兄ちゃんも教え方上手い。テキストの進め方を工夫しているし、「こういうところを直したい」というと練習を考えて応じてくれる。Anyways,と言うのがクセ(若者の流行り?)。
また「公用語化」の話。「中国語のほうが(母語として)話者は多いのに英語がいちおう世界共通語とされているのはなぜか?」。地理的に優勢、というのと、もうひとつは「政治的なパワー」だからとか。なるほど。言語は国家力のバロメーター。
こちらの先生が言うように「言語はアイデンティティ」(のかなりの部分を占める)と私も思う。自分で意識している以上にそうだろうなと思います。だから「社内英語公用語化」とか「キッズ・イングリッシュ」の必要性が個人的にはまったくもってわからない。
今日の先生はいちばん教えてもらっている人なので慣れてしまった分、素になるというか緊張が続かずへこたれる。英語については悲喜こもごも思うところあり、一時に比べてモチベーション落ちてるのがばれているであろうことも恥ずかしい。
言語は伝達の手段であり、それこそoverrateしてもしょうがないですが、やっぱり使ってこそのもの。私は「人が好き!」とか「社交的」なタイプではない(まるで逆)けど、それでも人と関わっていたい。がんばれないけどあきらめず、気長にやってこ…。
こちらの先生が言うように「言語はアイデンティティ」(のかなりの部分を占める)と私も思う。自分で意識している以上にそうだろうなと思います。だから「社内英語公用語化」とか「キッズ・イングリッシュ」の必要性が個人的にはまったくもってわからない。
今日の先生はいちばん教えてもらっている人なので慣れてしまった分、素になるというか緊張が続かずへこたれる。英語については悲喜こもごも思うところあり、一時に比べてモチベーション落ちてるのがばれているであろうことも恥ずかしい。
言語は伝達の手段であり、それこそoverrateしてもしょうがないですが、やっぱり使ってこそのもの。私は「人が好き!」とか「社交的」なタイプではない(まるで逆)けど、それでも人と関わっていたい。がんばれないけどあきらめず、気長にやってこ…。
「私の骨を返して!」と叫ぶブレナン博士@BONES。超クールだわ。。働く女の特殊な鑑だわね。
今日は中国の不可解な一連の事件についての記事を読んでディスカッションする予定でその顛末を一生懸命まとめていたらそうじゃなく、「その前にちょっと」と消費税増税について訊かれ(「それしか選択肢がない」という説明が政府からないので説得力ない)→野田首相をどう思うか(まOKと思う)→オリンピック誘致(何でいまさらまた)→テプコはなぜ国有化しない(ほんとですよ!)→日本の中流階級→英語公用語化→キッズスクールの増殖etc.と「わらしべ長者」式に話が転がったのでそこまでいかなかった。でもとても楽しかったです。
インストラクターで"good listener"というのを売りにしている人は多いけれど、今日の先生はまさにそれを「体現」してる。「ちゃんと聴いていますよ」というのを英語の先生として態度で示している。素晴らしいです。(他の人がいい加減なわけじゃないけど)やはり印象が違うし、こちらも頑張って話そうというキモチになる。そして会話を促すのも上手。教え方が板についているというか、上手な役者が自然であるように自然体で「先生」。こちらも鑑ですね。
(ヒマなので)「" 日本人に英会話を教える"というのはどういうことか?」「そこで何が提供されているのか(orされるべきか)」よく考える。英語で話をして間違いがあれば直す、というのもレッスンの一部だろうけれど、それだけでしょうか?(前回の先生はそれがメインだった)
「間違い直しを是非して欲しい」と生徒が思っていたり、ガッツがあったり、既にあるレベルまで到達してたり…の場合は有効かもしれない。が、私的な仮説としては「英語で話をする体験」を与えるのがひょっとしてネイティブ・スピーカーとのレッスンの意義としていちばん大きいのではと思っている。まさにそのまんま、ですが。
「英語を話したら通じた!」という独特のセンセーション。「間違い直し」だけならEランでもできるけど、それこそ相互のやりとりならではの、みずみずしい体験ではないか。
(とにかくヒマなので)「なぜ日本人は英語が苦手なのか?」「どうしたら学習が継続するか、やる気になるか」ていうのもよく考える。あれだけ熱狂的にTOEIC受けてる(or受けさせられてる)のになぜスコアはアジア一じゃないの?(まあトーイックは目安に過ぎないけれども)。
少なくとも中高であれだけ英語をやらされるので、基礎はあるはず。でも一般に苦手意識は強い。本当はできるのに「苦手」と思っている「だけ」の人は多いはず。だからレッスンで「オレ(わたし)って英語で話せてる!」ていう新鮮な成功体験を増やせると自信が学習を後押しするのではと思う。
上で書いた「英語で話をする体験」というのは、理想としては単に日本語を英語に置き換えるプロセス以上のものであってほしい。まず「自分の意見をもつ→それを英語で表す」ということだったり、英語の会話のノリみたいなものを得る。そういうのメソッドにできないかな…。
「主張する」習慣がそもそもない風土で(今日の先生は「日本のそういうとこが和む」そうです。西洋人はいちいち主張するので「疲れる」とか)、経営がベリー・ジャパニーズなまま「社内英語公用語化」って変ですよねっと言い放ち合う。
(職員がそもそも多国籍とか)必要なところは既に職場で英語で話してる。個人的には極端に言えば、英語専門職以外の社会人は自分の意見がありさえすれば今までに教わったぶんで乗り切れるはず!私は体育会系じゃないけど英語に関しては気合と態度て大切と思います(ざっくり言って会話の成り立ちが日英でかなり違うので、コンバットモードくらいで臨む)。一方、政治家はトーイック900軽くとるくらい英語やれ、と思う。
「犬の訓練と同じ」て私はよく思うけど、レッスンで「ほめる」のはほんとうに大事。簡単でいいから「その場で」よくほめる。もちろん大人でも。日本人は心理的ブロックが大きい気がするので、ポジティブな言葉かけは自信につながるし、大げさくらいでもいいと思う(妙にアッパーな雰囲気にしなくていいですが)。
「この頃、子どもの英会話スクールが増えてる気がしますがどう思いますか?」と先生に訊いたら、「わけわからない…」と小声で言ってておかしかった(ここでもやってるのに)。私もそう思うです。英語する時間あったら、子どもは遊んだらいいと思う。あと日本では「中流階級がとても多いのが興味深い」とも言っていた。英国出身の方とこれだけみっちり話すのは初めてで、それこそ苦手意識があったけどとても話しやすかった。
これだけつらつら書いたのも、「通じるってうれしい!」というベーシックな楽しさを思い出させてくれたレッスンだったから。やっぱりほめ上手で私は木に登りましたv。
今日は中国の不可解な一連の事件についての記事を読んでディスカッションする予定でその顛末を一生懸命まとめていたらそうじゃなく、「その前にちょっと」と消費税増税について訊かれ(「それしか選択肢がない」という説明が政府からないので説得力ない)→野田首相をどう思うか(まOKと思う)→オリンピック誘致(何でいまさらまた)→テプコはなぜ国有化しない(ほんとですよ!)→日本の中流階級→英語公用語化→キッズスクールの増殖etc.と「わらしべ長者」式に話が転がったのでそこまでいかなかった。でもとても楽しかったです。
インストラクターで"good listener"というのを売りにしている人は多いけれど、今日の先生はまさにそれを「体現」してる。「ちゃんと聴いていますよ」というのを英語の先生として態度で示している。素晴らしいです。(他の人がいい加減なわけじゃないけど)やはり印象が違うし、こちらも頑張って話そうというキモチになる。そして会話を促すのも上手。教え方が板についているというか、上手な役者が自然であるように自然体で「先生」。こちらも鑑ですね。
(ヒマなので)「" 日本人に英会話を教える"というのはどういうことか?」「そこで何が提供されているのか(orされるべきか)」よく考える。英語で話をして間違いがあれば直す、というのもレッスンの一部だろうけれど、それだけでしょうか?(前回の先生はそれがメインだった)
「間違い直しを是非して欲しい」と生徒が思っていたり、ガッツがあったり、既にあるレベルまで到達してたり…の場合は有効かもしれない。が、私的な仮説としては「英語で話をする体験」を与えるのがひょっとしてネイティブ・スピーカーとのレッスンの意義としていちばん大きいのではと思っている。まさにそのまんま、ですが。
「英語を話したら通じた!」という独特のセンセーション。「間違い直し」だけならEランでもできるけど、それこそ相互のやりとりならではの、みずみずしい体験ではないか。
(とにかくヒマなので)「なぜ日本人は英語が苦手なのか?」「どうしたら学習が継続するか、やる気になるか」ていうのもよく考える。あれだけ熱狂的にTOEIC受けてる(or受けさせられてる)のになぜスコアはアジア一じゃないの?(まあトーイックは目安に過ぎないけれども)。
少なくとも中高であれだけ英語をやらされるので、基礎はあるはず。でも一般に苦手意識は強い。本当はできるのに「苦手」と思っている「だけ」の人は多いはず。だからレッスンで「オレ(わたし)って英語で話せてる!」ていう新鮮な成功体験を増やせると自信が学習を後押しするのではと思う。
上で書いた「英語で話をする体験」というのは、理想としては単に日本語を英語に置き換えるプロセス以上のものであってほしい。まず「自分の意見をもつ→それを英語で表す」ということだったり、英語の会話のノリみたいなものを得る。そういうのメソッドにできないかな…。
「主張する」習慣がそもそもない風土で(今日の先生は「日本のそういうとこが和む」そうです。西洋人はいちいち主張するので「疲れる」とか)、経営がベリー・ジャパニーズなまま「社内英語公用語化」って変ですよねっと言い放ち合う。
(職員がそもそも多国籍とか)必要なところは既に職場で英語で話してる。個人的には極端に言えば、英語専門職以外の社会人は自分の意見がありさえすれば今までに教わったぶんで乗り切れるはず!私は体育会系じゃないけど英語に関しては気合と態度て大切と思います(ざっくり言って会話の成り立ちが日英でかなり違うので、コンバットモードくらいで臨む)。一方、政治家はトーイック900軽くとるくらい英語やれ、と思う。
「犬の訓練と同じ」て私はよく思うけど、レッスンで「ほめる」のはほんとうに大事。簡単でいいから「その場で」よくほめる。もちろん大人でも。日本人は心理的ブロックが大きい気がするので、ポジティブな言葉かけは自信につながるし、大げさくらいでもいいと思う(妙にアッパーな雰囲気にしなくていいですが)。
「この頃、子どもの英会話スクールが増えてる気がしますがどう思いますか?」と先生に訊いたら、「わけわからない…」と小声で言ってておかしかった(ここでもやってるのに)。私もそう思うです。英語する時間あったら、子どもは遊んだらいいと思う。あと日本では「中流階級がとても多いのが興味深い」とも言っていた。英国出身の方とこれだけみっちり話すのは初めてで、それこそ苦手意識があったけどとても話しやすかった。
これだけつらつら書いたのも、「通じるってうれしい!」というベーシックな楽しさを思い出させてくれたレッスンだったから。やっぱりほめ上手で私は木に登りましたv。
昨日の映画に背中を押され、古巣のグループが主催するイベントに早起きしてちょっとだけ出る。いつも思うけどこのオーガナイズ力はすごいわ。3人くらい体験談を聞いて英会話へ。
「厳しくていい先生だから」と勧められたその人はNZ出身だそう。確かに詰め詰めで進めるけど、2-wayになってないというか一方的な感じ。あまり愛想のない人なので、学習はするけど無愛想対決みたいになっちゃって、微妙。Warm-upで話したときの個人的なやりとりもちょっとひっかるところがあり、デリカシーがないんじゃ…と言ったらなんですが単に合わないのかもしれない。
自分が話したなかの単語で、"Road Movie""Yakuza"って何それ?知らない、と言われた。前者は少なくとも英語のウィキにあるし、後者もけっこう英語の辞書に載っている(日本にいるんだから知っておこうよ…)。あとで思ったけどその場で調べてみればよかったんじゃない?
「厳しくていい先生だから」と勧められたその人はNZ出身だそう。確かに詰め詰めで進めるけど、2-wayになってないというか一方的な感じ。あまり愛想のない人なので、学習はするけど無愛想対決みたいになっちゃって、微妙。Warm-upで話したときの個人的なやりとりもちょっとひっかるところがあり、デリカシーがないんじゃ…と言ったらなんですが単に合わないのかもしれない。
自分が話したなかの単語で、"Road Movie""Yakuza"って何それ?知らない、と言われた。前者は少なくとも英語のウィキにあるし、後者もけっこう英語の辞書に載っている(日本にいるんだから知っておこうよ…)。あとで思ったけどその場で調べてみればよかったんじゃない?
医者にやられても一日で起き上がるわたし。医者ったって「全知全能」じゃないもの。彼女が考えているより、世の中はもちょっとカラフルなんじゃないだろうか、と思う。「現実」にはいつかやられるかもしれないとしても、医者ごときにやられっぱなしではなくてよ。でもお薬はのみます。
ジョブフェアーにちょろっと行ってみる。実際の収穫はなかったですが、自分だけでなくこれほどたくさんの人が職(or「より良い職」)を求めていると知るのは慰めにはなるし、ブースの女性社員さんがばりばり英語で外国人に説明してるの聞くと「もっとやらにゃだめだなー」と思い知る。
その英語はDiscussionというやや傍系のテキスト使って進めることに。今日の先生はさわい兄ちゃんであの大雪の日は自転車こいで帰ったという(すごい)。仕事で何がいちばんストレスになるか?という話をしていて、私が「日本では”人間関係”じゃないですか」と言ったら、「アメリカでは“やりがいのなさ”」だと彼は言っていた。職場でファーストネームで呼ぶのは「普通」だけど、苗字で呼ぶ(“スミス!”とか)のはさらに親しさが進んだ表現になるのだそう。仲間意識のあらわれというか。なるほど~!そういえばよくTVドラマで呼び捨ててますね。
ジョブフェアーにちょろっと行ってみる。実際の収穫はなかったですが、自分だけでなくこれほどたくさんの人が職(or「より良い職」)を求めていると知るのは慰めにはなるし、ブースの女性社員さんがばりばり英語で外国人に説明してるの聞くと「もっとやらにゃだめだなー」と思い知る。
その英語はDiscussionというやや傍系のテキスト使って進めることに。今日の先生はさわい兄ちゃんであの大雪の日は自転車こいで帰ったという(すごい)。仕事で何がいちばんストレスになるか?という話をしていて、私が「日本では”人間関係”じゃないですか」と言ったら、「アメリカでは“やりがいのなさ”」だと彼は言っていた。職場でファーストネームで呼ぶのは「普通」だけど、苗字で呼ぶ(“スミス!”とか)のはさらに親しさが進んだ表現になるのだそう。仲間意識のあらわれというか。なるほど~!そういえばよくTVドラマで呼び捨ててますね。
英会話スクールではテキストを使わねばなりません。1レベル上がった、と喜んでいたけど、そのテキストが今までのと見たとこそんなに変わらない。どこが違うんですか?と訊いたら、実のところ難易度としてはあまり違わないのだそうだ。
自分が使ってるのは「ビジネス」編だけど…生ぬるい、と思った。「ガリ勉野郎」な私としては、せっかく上がるんだから、もっとチャレンジングなものをやる気十分に期待してたのにこれ?ビジネスならばなおさらがつがつやらねばならないのではないか。
でその辺のことを先生にも結構、言っちゃってたかもしれない。いや言ってたような気がする。日ごろからネイティブ好みの明るいパーソナルな話題がない上に難癖つけて、めんどくさい生徒リストに載ったかもしれない。あるとしたら。でもこのテキスト高いんだよほんとに。
こういうやり方が好きだったり合う人もいるのでしょうが、正直なとこ私にはよくできたテキストとも思えない。おとなしい羊の如くテキストに従っていれば、スピーキング力は上がっていくのか?
あくまでスイカ式仮説だが:
A(教わる側の要素:やる気など)×B(コンテンツ:講座、教材)×C(教える側の要素:技量、パーソナリティなど)(×任意のD:Aにコントロールできない外的、社会的な要素)→学びの成果なのでは、と個人的には思っている。
この大手スクールはCについて個々のインストラクター任せ、組織としてメソッドがないような印象が今までのところある。がっかり。だし、志低くないか?
このスクールは1回ごとのレッスン評価は生徒からまめにとって公表しているが、考えてみると「どのくらいスキルが伸びたか」は結果として出してない。後者は検証が難しいということもあるでしょうが、大人も通うスクールは勉強本位にできないところもあるだろうと思う。まぁいろんな理由で生徒をプッシュしにくいのだろう。
通う目的なり背景はそれぞれで、楽しいのがいいという人もいるだろうし…だけど私としては英語は「ツール」というだけでなく、探索し甲斐のある「美」があると思っている。私はシリアスにやりたいのです。
自分が使ってるのは「ビジネス」編だけど…生ぬるい、と思った。「ガリ勉野郎」な私としては、せっかく上がるんだから、もっとチャレンジングなものをやる気十分に期待してたのにこれ?ビジネスならばなおさらがつがつやらねばならないのではないか。
でその辺のことを先生にも結構、言っちゃってたかもしれない。いや言ってたような気がする。日ごろからネイティブ好みの明るいパーソナルな話題がない上に難癖つけて、めんどくさい生徒リストに載ったかもしれない。あるとしたら。でもこのテキスト高いんだよほんとに。
こういうやり方が好きだったり合う人もいるのでしょうが、正直なとこ私にはよくできたテキストとも思えない。おとなしい羊の如くテキストに従っていれば、スピーキング力は上がっていくのか?
あくまでスイカ式仮説だが:
A(教わる側の要素:やる気など)×B(コンテンツ:講座、教材)×C(教える側の要素:技量、パーソナリティなど)(×任意のD:Aにコントロールできない外的、社会的な要素)→学びの成果なのでは、と個人的には思っている。
この大手スクールはCについて個々のインストラクター任せ、組織としてメソッドがないような印象が今までのところある。がっかり。だし、志低くないか?
このスクールは1回ごとのレッスン評価は生徒からまめにとって公表しているが、考えてみると「どのくらいスキルが伸びたか」は結果として出してない。後者は検証が難しいということもあるでしょうが、大人も通うスクールは勉強本位にできないところもあるだろうと思う。まぁいろんな理由で生徒をプッシュしにくいのだろう。
通う目的なり背景はそれぞれで、楽しいのがいいという人もいるだろうし…だけど私としては英語は「ツール」というだけでなく、探索し甲斐のある「美」があると思っている。私はシリアスにやりたいのです。
英会話のテキスト1冊、終わったのでレベルちぇーっく。これにパスすると上のレベルに行けます。でないと給付金のキャッシュバックが受けられないので行かねばなりません。
先生に「ちょろいから平気~」と聞かされていたテストは雑談・余談をはさみつつカジュアルに終わった。が、合格するには12ある到達項目のうち10はクリアしないといけないそうで(汗)…難しいじゃん!それ事前に聞いていなくてよかったよ。
ともかくパス。がっつりしたテストじゃないけど、嬉し~。
今後のメモ:
(1)使い慣れた言い回しを使い回しがち(目が回るような表現…)なので、「勇気をもって」新しい言葉を使う。
(2)口語表現を増やす。私は帰国子女でもなく留学経験もない。ベースは「学校英語」「受験英語」だから文章で使うような堅苦しい単語が会話でも先に出ていると思われ。そうでなくget+...、take+...、come+...といった日常的なイディオムを口に出せるように。
(3)↑にも共通するが、言いたいことは大まかに伝えられるようになったので、次は「ナチュラルに」。たぶん会話でも自分はwordy(余計な言葉が多い)だと思うので、つとめて簡潔にする(関係詞でつながず、分けるとか)。
(4)さらに「状況に応じて適切に」。ちょっとした表現の違いで伝わるニュアンスがだいぶ変わる。その使い分け。たとえばI’ll tell him... vs.I’ll be sure to tell him...(電話の受け答えにおいて後者のほうが頼もしい。好感度上)。
(5)「英語らしさ」を意識する。会話における「英語っぽい」特徴を意識して拾う。たとえば英語の会話はお互いつないで続けてるんじゃ、とか日本語の1.5倍くらい大げさに言って平気ぽい、という仮説の検証。
テスターの先生に「ボディ・ランゲージやフィラーを上手く使っててナチュラル」とほめられたのは意外で嬉しかった。フィラー(filler:日本語でなんと呼ぶのかわからないけど「えーっと」「そうですね…」みたいな会話のつなぎ言葉のこと)はいつもの先生に教わったおかげ(「黙ってないでなんか言わないと」)。それ自体に意味はないけど役割は同じ。それでも言語によってフィラーも違うのは面白いことだと思う。
先生に「ちょろいから平気~」と聞かされていたテストは雑談・余談をはさみつつカジュアルに終わった。が、合格するには12ある到達項目のうち10はクリアしないといけないそうで(汗)…難しいじゃん!それ事前に聞いていなくてよかったよ。
ともかくパス。がっつりしたテストじゃないけど、嬉し~。
今後のメモ:
(1)使い慣れた言い回しを使い回しがち(目が回るような表現…)なので、「勇気をもって」新しい言葉を使う。
(2)口語表現を増やす。私は帰国子女でもなく留学経験もない。ベースは「学校英語」「受験英語」だから文章で使うような堅苦しい単語が会話でも先に出ていると思われ。そうでなくget+...、take+...、come+...といった日常的なイディオムを口に出せるように。
(3)↑にも共通するが、言いたいことは大まかに伝えられるようになったので、次は「ナチュラルに」。たぶん会話でも自分はwordy(余計な言葉が多い)だと思うので、つとめて簡潔にする(関係詞でつながず、分けるとか)。
(4)さらに「状況に応じて適切に」。ちょっとした表現の違いで伝わるニュアンスがだいぶ変わる。その使い分け。たとえばI’ll tell him... vs.I’ll be sure to tell him...(電話の受け答えにおいて後者のほうが頼もしい。好感度上)。
(5)「英語らしさ」を意識する。会話における「英語っぽい」特徴を意識して拾う。たとえば英語の会話はお互いつないで続けてるんじゃ、とか日本語の1.5倍くらい大げさに言って平気ぽい、という仮説の検証。
テスターの先生に「ボディ・ランゲージやフィラーを上手く使っててナチュラル」とほめられたのは意外で嬉しかった。フィラー(filler:日本語でなんと呼ぶのかわからないけど「えーっと」「そうですね…」みたいな会話のつなぎ言葉のこと)はいつもの先生に教わったおかげ(「黙ってないでなんか言わないと」)。それ自体に意味はないけど役割は同じ。それでも言語によってフィラーも違うのは面白いことだと思う。
Very Bunny
2012年1月13日 EL
無表情に思い詰めてるウサギが素敵過ぎるこの本(The Book of Bunny Suicides)はアマゾンで買いました。エルトン・ジョン、ヒュー・グラントも絶賛お薦め中。一部かなりブラックですが、オカシイ。こういうの大好き。引き続きインターネットは誘惑が多すぎ、しばらく近づかないほうがいいかも自分。
外国語の会話を学ぶとは結局、「状況に対処する」やり方を学ぶのではないだろうか。無慮千万―そんなにはないか―あるかもしれないシチュエーションにおいて、その言語で乗り切るべく言葉の使い方(フレーズからロジックの立て方)を学ぶ。なんとかさばいて局面を脱出できればいいわけで、精度や適切さなどをレベルに応じて上げてく。どんな状況においてもその人の強みを発揮できるとすごい、と思う。来週はテストですが、そんな私は身体も頭もいまいちめぐりが悪いような。すかすかしてるな。
外国語の会話を学ぶとは結局、「状況に対処する」やり方を学ぶのではないだろうか。無慮千万―そんなにはないか―あるかもしれないシチュエーションにおいて、その言語で乗り切るべく言葉の使い方(フレーズからロジックの立て方)を学ぶ。なんとかさばいて局面を脱出できればいいわけで、精度や適切さなどをレベルに応じて上げてく。どんな状況においてもその人の強みを発揮できるとすごい、と思う。来週はテストですが、そんな私は身体も頭もいまいちめぐりが悪いような。すかすかしてるな。
「生まれ変わったら何になりたい?」と訊かれて、「木になりたい」と答えた。
屋久島、とかだったら素晴らし過ぎるがそれほど徳を積んでもいないので、どこかひっそりとした渓谷の、清流のほとりで木になりたい。木は求められることもないし、自ら求め過ぎることもない。平和で静かに過ごせそうな気がします。人間はもういい。
でもっとつっかえずに説明できればいいんだけど。私の受講するコースにはもれなくTOEICがついてくるので3月に受験けってい(泣)。
屋久島、とかだったら素晴らし過ぎるがそれほど徳を積んでもいないので、どこかひっそりとした渓谷の、清流のほとりで木になりたい。木は求められることもないし、自ら求め過ぎることもない。平和で静かに過ごせそうな気がします。人間はもういい。
でもっとつっかえずに説明できればいいんだけど。私の受講するコースにはもれなくTOEICがついてくるので3月に受験けってい(泣)。
メンクリ。人が大勢いたものの流れが早くてほっとしていたら私の前の奥様が長い。ほんっとに長い。お前な。「どうせ旦那や子どもの話でしょ(おおあたり)」と先生に八つ当たり。持ってる病人はキライだ。私はよそで言えないことを話す。母は「孤独というものをおそらく知らないでしょう」と先生。そうだと思います。そして自分たちが恵まれていることに気づいてない。
英語。「トラディショナルな正月でした」とホリデイ報告、そしてお気に入り神社の説明。今日のインストラクターは毎年とにかく「中吉」を引き続けているそうだ。それもある意味、特殊にラッキーなのでは。外国人(ノンネイティブ)に英会話を教えるってどういうことなの、と考え続けている。会話のフレーズを渡すことだけ、ではないはず。
英語。「トラディショナルな正月でした」とホリデイ報告、そしてお気に入り神社の説明。今日のインストラクターは毎年とにかく「中吉」を引き続けているそうだ。それもある意味、特殊にラッキーなのでは。外国人(ノンネイティブ)に英会話を教えるってどういうことなの、と考え続けている。会話のフレーズを渡すことだけ、ではないはず。
CIWS、久しぶり~。コンタクトしたりしなかったり、ペアの相手と距離をさまざまに変えながらするワークはやってても見てても面白かった。質感イロイロ。
CIのいろんな定番テクを教わったとしても、基本的に自分は人に緊張するタイプなので、そもそもの話だがそのハードルがある。コンタクト上手な人たちがするように、お互い楽ちんなままシームレスにつながるインプロができたらいいなぁ、と思うものの、人に対する緊張や焦り、遠慮とかどうしたらいいのかな。ないことにはしたくない、というか、大事なことだと思うけど。
年内EL納め。来春、受験の姪から英語についての通(ツウ)な質問がときどきメールでとんでくる。それについて先生に訊いてて、「英語における主語の省略」とか「主語が動詞を決定する」とかハードコアな言語学の話(笑)をつれづれ。会話のきまりフレーズなんかを練習してるとたそがれてくる時もままありますが、この先生と言語オタクな話をするのはとても楽しい。いまどきな日本語で「逆に」というのが彼のお気に入りだそうだが、たいてい逆の話になっていないので私なんかはしばしば聞いてて頭がよじれてきますね。
CIのいろんな定番テクを教わったとしても、基本的に自分は人に緊張するタイプなので、そもそもの話だがそのハードルがある。コンタクト上手な人たちがするように、お互い楽ちんなままシームレスにつながるインプロができたらいいなぁ、と思うものの、人に対する緊張や焦り、遠慮とかどうしたらいいのかな。ないことにはしたくない、というか、大事なことだと思うけど。
年内EL納め。来春、受験の姪から英語についての通(ツウ)な質問がときどきメールでとんでくる。それについて先生に訊いてて、「英語における主語の省略」とか「主語が動詞を決定する」とかハードコアな言語学の話(笑)をつれづれ。会話のきまりフレーズなんかを練習してるとたそがれてくる時もままありますが、この先生と言語オタクな話をするのはとても楽しい。いまどきな日本語で「逆に」というのが彼のお気に入りだそうだが、たいてい逆の話になっていないので私なんかはしばしば聞いてて頭がよじれてきますね。
クリスマス・イシュー
2011年12月21日 ELタフなシーズンであり、今年はひときわ厳しい。としか言えない(言わなかったけど)のでクリスマスの話でつっこむのはやめてほしかったのだが(てか宗教の問題だから話題にしないのでは、と思っていた)。でもあとで考えたら気を遣わせてしまったようで悪かったと思う。申し訳ないけどしょうがない。
「苦情を言う」トピックを教わってなぜかパワレスな気もちになる。「フェアじゃない」て言っていいなんて、そういう発想自体が私にはなかったよ。ということに気がついた。それって言えば意味あるわけ?世の中は不公平にできている。That’s the way it is.とか言ってないで淡々と「そういうものだ」と覚えりゃいいのでしょう。
ある人に呼び出されて行ったら、件の若い女がつーんとしてて話にならない。頭にきてスチールの扉を何度も蹴り飛ばそうとするが手ごたえがなくイライラする、という夢〔夢日記111221〕。寝つこうとするとき呼吸が浅くなったり、ときどき止まったりする件。
「苦情を言う」トピックを教わってなぜかパワレスな気もちになる。「フェアじゃない」て言っていいなんて、そういう発想自体が私にはなかったよ。ということに気がついた。それって言えば意味あるわけ?世の中は不公平にできている。That’s the way it is.とか言ってないで淡々と「そういうものだ」と覚えりゃいいのでしょう。
ある人に呼び出されて行ったら、件の若い女がつーんとしてて話にならない。頭にきてスチールの扉を何度も蹴り飛ばそうとするが手ごたえがなくイライラする、という夢〔夢日記111221〕。寝つこうとするとき呼吸が浅くなったり、ときどき止まったりする件。
英語ヴォイトレのセミナーへ行く。といっても歌の練習ではなく「発音力」の向上を目指すもの。以下、メモ(私の理解によるものなので、精度はざっくりです。スミマセン):
●英語は「息」の言語、日本語は「声」の言語
…これは本当に目からウロコ。英語は「音」を出しているわけではなく、「息」
でつくっている。唇の開き(閉じ)具合、舌の巻き方、当てる場所によって口蓋の空間が変化する、それによってそこを通る息が変化する。岩によって変わる流れとか、木立を吹き抜ける風、自然音みたいな感じ。
●英語は息で子音を形成する。
…母音とかr,l音ばかりに気をとられがちだが、「息(のみ)で子音をつくる」というのが実はかなりポイント。というのも日本語は常に母音を伴うから、子音の発音時に母音を入れてしまいやすい(いわゆるカタカナ発音)。例えば[k]の発音は[k+u](ク)ではない。
だから日本人は子音の連続に苦労する。私も子音プラスrが特に苦手。舌が巻き上がれないっ。
●英語は子音のリズムで、日本語は母音のリズムで話す。
…日本語は高低の言語、英語は強弱の言語でもある(アクセント)。日本語のほうが大波小波、英語は平坦というイメージ。この辺の話は「英語文化においてラップ・ミュージックが生まれた」歴史の必然と私的にはリンクした。
講師によると「日本語は韻を踏むことを尊ばない、独特の言語」。となると「音声として日本語の美学はどこにあるのか」「日本語のラップは自然としてどういう音と結びつくか」という疑問(オフ・ビートなのかも)。
●英語は「一息一語、一息一文」
…やはり英語は日本語に比べてmusical, physicalだと感じる。↑こういうのはダンスっぽい発想。わかりやすい。これが言えるということは身体に自然ということだと思う。
腹式呼吸も教わる(ネイティブスピーカーが発音するとき息を吐く量は、日本人のそれに比べて半端なく多い)。ダンスと同じだけど違うところは、ダンスが細く長く息を吐くのに対して、英語の発音練習においては口をひらいて(ノドを広げて)息を吐き出す。
英語は音じゃなくて「息で出す」。これがとにかく新鮮だった。日本語と英語は言語の構造としてかなーり違う。刺激的で面白いセミナーでした。
●英語は「息」の言語、日本語は「声」の言語
…これは本当に目からウロコ。英語は「音」を出しているわけではなく、「息」
でつくっている。唇の開き(閉じ)具合、舌の巻き方、当てる場所によって口蓋の空間が変化する、それによってそこを通る息が変化する。岩によって変わる流れとか、木立を吹き抜ける風、自然音みたいな感じ。
●英語は息で子音を形成する。
…母音とかr,l音ばかりに気をとられがちだが、「息(のみ)で子音をつくる」というのが実はかなりポイント。というのも日本語は常に母音を伴うから、子音の発音時に母音を入れてしまいやすい(いわゆるカタカナ発音)。例えば[k]の発音は[k+u](ク)ではない。
だから日本人は子音の連続に苦労する。私も子音プラスrが特に苦手。舌が巻き上がれないっ。
●英語は子音のリズムで、日本語は母音のリズムで話す。
…日本語は高低の言語、英語は強弱の言語でもある(アクセント)。日本語のほうが大波小波、英語は平坦というイメージ。この辺の話は「英語文化においてラップ・ミュージックが生まれた」歴史の必然と私的にはリンクした。
講師によると「日本語は韻を踏むことを尊ばない、独特の言語」。となると「音声として日本語の美学はどこにあるのか」「日本語のラップは自然としてどういう音と結びつくか」という疑問(オフ・ビートなのかも)。
●英語は「一息一語、一息一文」
…やはり英語は日本語に比べてmusical, physicalだと感じる。↑こういうのはダンスっぽい発想。わかりやすい。これが言えるということは身体に自然ということだと思う。
腹式呼吸も教わる(ネイティブスピーカーが発音するとき息を吐く量は、日本人のそれに比べて半端なく多い)。ダンスと同じだけど違うところは、ダンスが細く長く息を吐くのに対して、英語の発音練習においては口をひらいて(ノドを広げて)息を吐き出す。
英語は音じゃなくて「息で出す」。これがとにかく新鮮だった。日本語と英語は言語の構造としてかなーり違う。刺激的で面白いセミナーでした。
先週、ネイティブスピーカー様に見てもらった課題をさらに直し、見てもらう。豪華だわね。それにしても日本語の書きものセンサーが英語では効かない。とはいえ書き直した部分は赤が入らず、フロー(構成)もスムース、だーいぶクリアになったそうでよかった。よかった、と思ったら気が抜けて英語脳停止。自分ユースレスなままレッスン終わる。
やさぐれてたらアマゾンで音楽ぼーっと衝動買い。情報を選り分けるのも、人を選り分けるのにも、自分にも疲れてきた。どっか行こう。
やさぐれてたらアマゾンで音楽ぼーっと衝動買い。情報を選り分けるのも、人を選り分けるのにも、自分にも疲れてきた。どっか行こう。